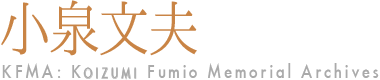展示企画「邦楽器が受け継ぐ 技・形・音 こめられた丹精」が終了いたしました。
1900人の方にご来場いただきました。心よりお礼申し上げます。
展示企画
邦楽器が受け継ぐ 技・形・音 こめられた丹精
The Arts, Forms, Sounds between craftsmen and traditional Japanese musical instruments

| 会期 | 平成26年11月20日(木)〜11月30日(日) Nov 11 (Thu) – Nov 30 (Sun), 2014 |
| 時間 | 10時半〜16時半|入館無料、会期中無休 10:30-16:30│Admission is free. |
| 場所 | 東京藝術大学正木記念館1階 Masaki Memorial Gallery of the University Art Museum 1F, Tokyo University of the Arts |
| 製作 | 小泉文夫記念資料室 |
| 主催 | 東京藝術大学 |
| 助成 | 日本学術振興会 |
| 後援 | 台東区・台東区教育委員会・東京邦楽器商工業協同組合 |
| 協力 | 根ぎし 菊岡三絃店・有限会社 南部屋五郎右衛門・株式会社岡田屋布施・宮本卯之助商店・大塚竹管楽器・篠原まるよし風鈴・丸三ハシモト株式会社・チーガーの桃原・琉球楽器新栄堂・舞具工房あける |
| アクセス | JR上野駅公園口徒歩10分・京成上野駅徒歩15分・東京メトロ銀座線/日比谷線上野駅徒歩15分 |
| 問合わせ | 東京藝術大学音楽学部 小泉文夫記念資料室 〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8 TEL: 050-5525-2381(留守番電話の場合もあります) Email: fumioma@ms.geidai.ac.jp |
Organized by Tokyo University of the Arts. Patronized by Shinagawa Ward; Tokyo Traditional Japanese Musical Instruments Makers Co-operation. Supported by Japan Society for Promotion of Science. Incorporated with Negishi Kikuoka Sangen Ten; Nanbuya-Goroemon Ltd.; Okadaya-Fuse Co., Ltd.; Miyamoto Unosuke Shoten; Otsuka Chikukan Gakki; Shinohara Maruyoshi Furin; Marusan Hashimoto Co.; Chiga no Tobaru; Ryukyu Gakki Shin’eido; Bugu Kobo Akeru. Produced by Koizumi Fumio Memorial Archives, Department of Music, Tokyo University of the Arts.
展覧会概要
邦楽器は、発音機能と、物としての美しさをかねそなえた究極の工芸品です。洋楽器の多くは大量生産を前提とする工業製品ですが、邦楽器では、今なお複雑な製作過程のほとんどを、職人の手作業に負っています。一工程たりともおろそかにしない姿は、まさに「丹精」とよぶことができるでしょう。またその精緻さは、世界的にも驚異的なレベルにあります。本展は、こうした邦楽器の製作過程に光をあて、楽器に集積した知恵と技をあらためてほり起こします。
企画にあたっては、邦楽器の製作と地域の特性との関連にも注目します。東京藝大のおかれた台東区など下町一帯は、かつて江戸時代の花柳文化の中心地でした。また明治期の邦楽隆盛を背景に、邦楽従事者や邦楽器製作者も数多く存在していました。その歴史をひもときながら、台東区を中心とした邦楽器製作者の方々に協力をあおぎ、実物資料と写真、動画、実演をまじえて、代表的邦楽器の製作過程をみつめます。
Traditional Japanese musical instruments are ultimate artifacts which combine sound producing structure and the beauty of objects. As contrasted to Western musical instruments which almost are mass-produced industrial products, complicated producing procedures of Japanese traditional instruments are still carried out by hands of craftsmen. This exhibition introduces their producing procedures to which the craftsmen spare no pains, and tries to search wisdom and skills of making instruments. Demonstrations of producing the shamisen and wadaiko will be also given during the exhibition.
実演
三味線の革張り(根ぎし 菊岡三絃店)
11月22日(土)13:00〜
11月23日(日)13:00〜、11月24日(月祝)13:00〜
太鼓の革張り(有限会社南部屋五郎右衛門)
11月29日(土) 10:30〜、 13:30〜
関連企画(体験型)
三味線は「わざ」のかたまりだ!さぐろう伝統楽器の世界
11月22日(土)
出演:小島直文・関口奈々恵(三味線)、小林百合(唄)、村尾麻里子(唄)
対象:台東区内の中学生・高校生20名
助成:ひらめき☆ときめきサイエンス KAKENHI
関連企画
上方落語のハメモノ・太鼓
11月29日(土)
出演:林家染雀、笑福亭喬若、はやしや絹代(三味線)
対象:60名
助成:藝大フレンズ賛助金助成事業
展示風景
正木記念館入口
三味線の仲間――本土の三味線、沖縄の三線と胡弓(クーチョー)
三味線
三味線は、琉球に渡った中国の三弦を起源とし、通説によると、本土へは永禄年間(1558-1570)に伝来したと言われる。以後、約三百年にわたって、三味線は「うた」や「語り」の伴奏楽器として、江戸音楽文化の華となる。三味線をともなうジャンルの多様さは、三味線が人々を虜にした度合いの高さを物語る、何よりの証拠だろう。弾き手や聴き手がこの楽器に傾けたエネルギーは、三味線作りの精巧さに、何よりもはっきりと反映されたのではないか。職人は、一点ごとに異なる木材の木目や重量をその都度吟味し、各部位を切り出す。これを出発点として、百以上にも分かれた複雑な工程は、執拗なまでに手作業へのこだわりに貫かれている。
営々と受け継がれた三味線作りも、他の伝統文化と同様、克服すべき課題をかかえている。素材の入手の難しさに加えて、三味線人口の低下も、近年、恒常的な問題である。小中学校の教育指導要領に、日本の伝統楽器に触れるカリキュラムが導入されたとはいえ、その効果が目に見えて顕われるのは、まだまだ先であろう。津軽三味線や沖縄の三線は一過性の流行をみたが、それが三味線全般への興味を喚起するには至らなかった。
幾重にも問題が立ちはだかる中、職人の高齢化は進む。高級三味線の象徴だった「綾杉彫り」も、すでに関東地方では伝承者が絶えたという。三味線製作技術の継承は、瀬戸際にさしかかって久しい。市場原理では解決できない技術の継承問題を、演奏者、聴衆、教育者、文化行政も、別の観点から考えるべきではないだろうか。
技の粋を集めた三味線作り
三味線の胴と棹の製作は、別々の職人が担当する。「胴作りには、棹の重さも考慮し、楽器の最終的なバランスを定める責任が託される。棹作りはまったく別の仕事」、と胴職人は語る。そして、弾き手に即した楽器の姿を想像しながら、望ましい音質や重さ、感触を生み出すのが、胴の製作過程なのだ、という。
分業の目的は、胴と棹の製作を分け、職人一人当たりの作業負担を減らし、双方の作業精度をあげることだったと思われる。それが年月を経て、強い自負を秘めた作業へと昇華した点は印象深い。とはいえ、部外者からすれば、胴も棹も、想像を絶する膨大な時間と手間を要する点で、まったく互角である。端的な例が、胴、棹、天神いずれの部位にも必要な「磨き」の作業であろう。とくに棹の控えめな光沢と、滑らかな手触りは、粗さの違ういくつもの砥石で木を磨きこんで、はじめて得られるものだ。三味線職人の丹精がきわだつ部分である。木を石で磨くという実に意外な方法は、他の木工作業でも例はなく、三味線独特の技法である。おそらくこれも、紅木(コウキ)や紫檀(シタン)、欅(ケヤキ)、花櫚(カリン)など、非常に硬くて高密度の木材を相手にするうちに、見つけた「技」の一つと言えそうだ。
木材調達の難しさ
良質な木材の入手も容易ではない。紅木をはじめ、三味線の素材は、インドや東南アジアから100パーセント輸入に頼る。しかも高級木材の紅木は、家具製作などで引く手あまた、過剰な伐採で資源の枯渇が問題視されるほどだ。
猫革、犬革にかわる第三の革はあるか?
三味線作りの最大の問題は、胴皮の入手が難しいことである。1973年に動物愛護法が施行されて以来、国内では猫犬の皮が獲れなくなった。1990年に、殺処分となる猫犬の一部を用いることが条例化されたが、たとえ条件に合った皮が獲れたとしても、三味線の皮職人の手に届くまでに、時間がかかりすぎる。皮の鮮度が命の作業にとって、これは致命的な障害である。また現在、猫皮は台湾と中国、犬皮はタイから大部分を輸入するが、これらの地域でも捕獲の見通しは危うく、状況は厳しさを増すばかりである。
猫や犬にかわる素材として、丈夫で面積も広いカンガルーの皮は有望視される。1980年代には、東京都がバックアップし、故菊岡忍東京藝術大学邦楽科元教授が、三味線職人と共同で、カンガルー皮の実用化を検討した。しかし、カンガルーは好戦的で傷も多く、実用化には至っていない。
三線
三線は、14~15世紀に中国福建から琉球にもたらしたと言われる。福建のローカルな三弦は、揚子江下流域に分布する小三弦(シアオサンシエン)より小ぶりで、全長が85センチ 程度。現行の沖縄三線とほぼ同じ大きさである。三線史については多著に譲り、ここでは三線製作自体に目を向ける。
三線は、歴史的名工が考案した棹の形状にもとづき、以下のとおり分類される。南風原(フェーバル)型、知念大工(チネンデーク)型、久場春殿(クバシュンデン)型、久葉の骨(クバヌフニ)型、真壁(マカビ)型、平仲知念(ヒラナカチネン)型、与那城(ヨナグシク)型。小泉文夫記念資料室がチィーガの桃原を訪問した際に、胴の内部にも多様な細工が施されていることを確認した。本土の三味線胴と同様に、綾杉彫りを施した、という報告例もあり、今後、三線の胴については、さらなる探求が必要とおもわれる。
本土の三味線は、多様なジャンルに対応するため、異なる大きさや形状が生じたが、沖縄の状況は異なる。かつての名工が複数の型を作った理由も、形状の違いが音響に与える影響も、今後調査すべき課題である。ともかく、実質的な音響の決め手となる胴よりも、沖縄の人々は棹を重視し、演奏せずに棹のみ床の間に飾るなど、一種の権威すら感じている観がある。現在は、真壁がもっとも一般的で、与那城がこれに続く。
製作の現状をみると、本土の三味線同様、さまざまな問題を抱えている。素材調達の難しさはもちろんのこと、職人がカバーする技術の幅や作業内容の縮小も深刻な様相を呈する。たとえば胴を作る職人が激減し、輸入品に頼らざるをえない状況にあることは、本来的な楽器作りの「体力」低下を示唆する、といえるだろう。また、真壁と与那城を除くと、他の型を作れる職人はすでに第二次世界大戦前から、実質存在しなかったという。2000年代前半の沖縄ブームに合わせて、にわかに盛り上がった三線ブームは、外国産の安価な製品との競合をまねいた。その結果、沖縄では多くの職人が三線作りを断念し、ほんらいの伝統が受け継がれなくなる、という皮肉な現象も生じたのである。
素材調達の問題
一つは、三線の胴に張るニシキヘビの皮が入手困難なことである。希少動物の保護が急務となった今日、楽器用の捕獲は何かと風当りが強い。現在は、本革のかわり、ニシキヘビの柄をプリントした合成皮革を用いた三線も、多々出まわっている。木材も、「くるち」(沖縄原産の高級木材)がもっとも理想的とされてきたが、「くるち」はすでに自生せず、木材は全て輸入に頼る。
胡弓
胡弓は、沖縄本土ではおもに古典音楽の伴奏で用いる。三線にくらべて圧倒的に演奏者は少ない。胡弓は三線から作られた、という逸話が示すとおり、弦は本来は3本であるが、近年、4本弦の胡弓が作られ、3本弦よりも幅広い音域を得た。胡弓の製作は、通例、三弦の製作者が兼ねるが、製作者の人数は沖縄全島でもきわめて少数である。需要も少ないので、生産量との均衡はとれている。その意味では、後継者問題は、三線ほど深刻ではないと言えそうだ。
糸(弦/絃)*
糸
絹弦を張った弦鳴楽器は、古くからユーラシア大陸で広範に用いられてきた。ことに、桑材の胴と絹弦の相性の良さは、民族をこえて意識された観がある。
とはいえ、時代が下るにつれて、中央アジアや西アジアでは、絹弦はガットや金属弦にとってかわられた。また、絹弦の牙城の一角であった中国でも、近現代では目指す音楽性の違いから、絹弦の存在感がすっかり薄れてしまった。大きなホールで鳴り響くオーケストラと伍すためには、絹弦をあっさりと淘汰し、いさぎよく金属弦に代えるべきだ、と考えたためである。
いっぽう日本や韓国では、絹弦への愛着は依然としてかわらず、三味線やコムンゴに金属弦を張る試みなど、およそ考えられない状況である。絹弦が持つふくよかな音色を伴ってこそ、伝統音楽あるいは伝統楽器のアイデンティティが保たれる、というのが両地域に共通する観念ではないだろうか。強度こそガットや金属その他に劣るとはいえ、音響の豊かさにおいては、たしかに絹ほど優れた素材はあるまい。
絹弦は、「絹」を素材としながら、ふだん我々が絹に抱くイメージとは、意外なほどかけ離れた固さをもっている。服飾に用いる絹糸は、製糸の段階で表面を固める硬タンパク質(セリシン)を取り除き、内側の繊維素(フィブロイン)のみを用いる。このため絹特有な柔らかさや光沢が生まれる。いっぽう絹弦の原料ではセリシンをあえて残し、糸に腰をもたせる。さらにかき餅の糊で固め、縒りを加えることで、演奏に耐える適度な張りと強度を与えるのである。
現在、絹弦製造の精緻さと完成度において、日本を凌ぐ地域はないだろう。金属弦に傾きすぎた反動で、中国の二胡や古琴の一部演奏家の中には、実験的に絹弦を使う者も現れ始めている。しかし、長らく絹弦を放置してきた報いで、太さや強度、色、音質、どの観点からみても、演奏家の要求を満足させるレベルには至っていない。もちろん、その状態だからこそ、昔の鄙びた味わいを再現できる、という主張もあるのだが。
本展がご紹介する丸三ハシモト株式会社の絹糸製造過程は、作業の一つ一つが淀みなく連なり、製作作業全体が一つの完成された作品のようだ。こうした糸職人たちの丹精が、演奏を力強く確実に支えているのである。
※弦/絃の表記について
本展では、地域やジャンル内の慣例に従い、本土の弦鳴楽器には「絃」、沖縄ならびに楽器学用語として「弦」を用いた。
太鼓・鳴り物・玩具
太鼓:下町文化のシンボル
東京の下町は、江戸時代から祭礼の一大中心地であり、三社祭(浅草寺、台東区)、江戸三大祭りの神田祭(神田神社、千代田区)、山王祭(日枝神社、千代田区)、深沢祭(富岡八幡宮、江東区)など、数多くの祭礼がもよおされる。いっぽう、神社仏閣の祭礼で祭り囃子の核となる太鼓の製作も、江戸時代の下町を根拠地とした皮革加工業と、深いかかわりを持っていた。
江戸時代、浅草の今戸地区(現台東区北部。墨田区向島と境を接する地域)は、今戸町と浅草新町の2地区に分かれ、牛馬の解体処理や、太鼓製作を含む皮革産業の専業民(「長吏」と自称)が集中する地域であった。皮革業者を含めて、江戸時代にはいわゆる被差別民の待遇に甘んじた階層が存在した。当時、彼らを全関東規模で独占的に監督したのが、弾左衛門(被差別民の頭領、世襲の一家)である。同家は浅草新町に代々屋敷を構え、江戸幕府に対して、被差別民を治外法権におくほど、隠然たる勢力と巨万の富を誇った。明治維新後は、一早く洋風の生活に目を向け、革靴の製造に手を染めるなど、浅草が靴産業の中心として一時代を画す発端を作った。
現在、浅草を中心とする下町には、多くの太鼓店が軒を並べ、太鼓の製作と革の張替えを請け負う。本展でご協力いただく有限会社南部屋五郎右衛門は、浅草新町で元禄2年(1689)に創業。江戸時代以来の伝統を継承し、全国的にその名を知られる太鼓店である。また株式会社岡田屋布施は天保6年(1835)に浅草で創業。初代が皮革業者と楽器職人を仲介したことから、太鼓を含む楽器製造業に進出した。さらに、株式会社宮本卯之助商店は、文久元年(1861)土浦で初代が太鼓店を創業し、明治26年(1893)四代目の代に浅草に出店した。下町独自の社会的背景―皮革加工業の伝統、寺社仏閣の祭礼、さらに江戸文化の一拠点となった吉原遊郭など―が幾重にも重なりあって、太鼓製作者や販売者を江戸/東京によびこみ、さらには関連邦楽器の販売までをも促した、といえるだろう。
なお、多くの太鼓店では、太鼓のほかに祭りの神輿の製作販売を行うものが多い。各店が取扱いを始めたのは、おおむね「江戸神輿」が定着する大正時代以降のことである。昭和に入ると、平成天皇の誕生で祝賀ムードが高まり、神輿の新調が相次いだ、というエピソードもある。
鳴り物
玩具:ビードロ(ぽっぺん)
本展では台東区で製作されているビードロを取り上げた。
ビードロはガラス製の、首の細長いフラスコ状の玩具。管の先端をくわえて、ゆっくりと息を吹き込むと、底部が押されて「ぽっ」と音がなり、息を吹くのを止めると、押された部分が自然に戻って「ぺ」と鳴る。この音から「ぽっぺん」とも呼ばれる。ビードロは江戸後期に中国から伝わり、明治中期に大流行した。正月にビードロを吹くと厄よけになると言われ、破魔矢と同じく正月の縁起物として、寺院や神社で授与された時代もあった。しかし、壊れやすく、不注意で怪我をするなどの理由で、授与されなくなった。なお、「ビードロ」の語源は、ポルトガル語のvidro(ガラスの意味)である。
篠笛
篠笛と増える祭囃子のアマチュア人口
祭囃子といえば、神輿の担ぎ手同様、氏子=素人が担うものと思いがちである。だが、「江戸囃子」の本元である「江戸」では、祭り囃子は本来プロの神楽師たちの独壇場で、素人がかかわる余地はなかった。
江戸の囃子事情をふりかえると、少々込み入った歴史が浮かびあがる。江戸時代以降、伊勢神宮や熱田神宮が、神楽囃子を伴う獅子舞を諸国に差し向け、神宮詣でにかわる「代神楽(現在は「太神楽」が一般的)」として人気を集めた。正月の風物詩である各戸まわりの獅子舞は、ここに発する。17世紀の後半には、熱田神宮の代神楽で江戸に移住する者が増え、神田明神や山王権現の祭りにも関わり始めた。こうして神楽師たちは江戸の地場の祭礼にも根をおろして行く。独楽回しなど縁起のよい曲芸、といったイメージが強い太神楽だが、かつては神事と強く結びつく集団だったのである。
熱田神宮系代神楽の一支、「丸一」は、現在もつづく数少ない太神楽の集団だ。東都葛西囃子睦会の矢作伸二氏は、丸一についてこう語る:「第二次世界大戦前後まで、毎年、年の瀬には丸一太神楽に“マルイチ”と書かれた胴掛けを買いに行ったものだ。その布を桶胴に付ければ、正月に獅子舞を行なう許可を丸一から得たことになる(2000年6月8日談)」。この証言は、神楽師の権限を脅かさない、という不文律を示すものだろう。獅子舞に限らず、祭り囃子を仕切った神楽師たちは、様々な祭礼に出向き演奏を行った。江戸の祭礼で用いた山車が地方に引き取られると、山車の「嫁入り先」にも出張した。
しかし、昭和30年代には、祭りをとりまく環境は一変する。経済成長で都市人口は急増し、道路交通法が施行(1960)された。また、戦時中に途絶えた祭りも復活し、混乱を避けるためもあって、徐々に祭礼の週末開催が定着した。すると開催日が複数の祭礼で重なり、神楽師不足のためついに素人登場、という経過をたどった。小泉資料室がインタビューを行った篠笛製作業者によると、1960年代の売上げ急増で自社ビルが建ったという。祭り囃子がアマチュアに開かれた影響の大きさが、この証言ひとつで十分伝わるだろう。なお、現在の三社祭、山王祭など、江戸囃子系統の祭りでは、プロの囃子奏者、近郊のセミプロ(葛西囃子メンバーなど)、地元のアマチュアが混在する。
篠笛製作の諸環境と問題点
今回ご協力いただいた東京下町の主な篠笛工房は、地方出身の創業者が大正年間に東京で工房を持った点が共通する。経営はごく小規模な家内工業だが、直系の血縁に技術を伝えるとは限らず、義弟や娘の配偶者なども後継者となってきた。 現在は、製品の主流が祭り笛であるため、どの工房でも、春から夏に集中的に生産し秋の祭礼に間に合わせることが、年間の共通スケジュールとなっているようだ、竹は山から切り出した後、一定の太さと長さにしたがって切断し、6月の梅雨期に天日干しをする工程も共通するが、細かいレベルで工房ごとにノウハウもかなり異なるようである。
現在のところ、篠笛人気もあって、安定した消費量に恵まれている。しかし、素材となる良質な女竹が入手しにくくなり、また竹の伐採者がいなくなったことが最大の問題である。また一度に大量の竹を購入するため、乾燥段階でカビが生えて大きな損害を出す危険とも隣り合わせである。
次世代への技の継承については、跡継ぎがおらず廃業の危機にみまわれる店もある一方、若後継者を育成し、製造業を継続している店もある。 また、他業者や外国製品との競争は熾烈であり、独自の商品をブランド化するなど、対策を講じる場合もある。
四つ竹
四つ竹
琉球古典舞踊や沖縄の民俗芸能などで使う竹製の体鳴楽器。両手に2枚ずつ持ち、手の中で軽く打合せて「カチカチ」とリズムをとる。長さ:9〜13.5cm、幅:3.5〜5cm、厚み:8mm〜1.1cm 程度。表は黒、裏は紅色を塗り、房を付ける。
四つ竹を用いた、もっとも有名な琉球古典舞踊は、「踊こはでさ(ウドゥイクワディサ)」であり、歌の歌詞にも四つ竹が読み込まれている。踊り手は大きな花笠と紅型衣装を身に着け、四つ竹を打ち鳴らしながら優雅に踊る。四つ竹は、中国から琉球王府時代に伝来した可能性も指摘されている。現代の中国でも、四つ竹の類似楽器が、中国南方の語り物音楽に見出される。福建省の「南音」で用いる「四塊(スークァイ)」がそれで、奏法も音色も四つ竹に近い。